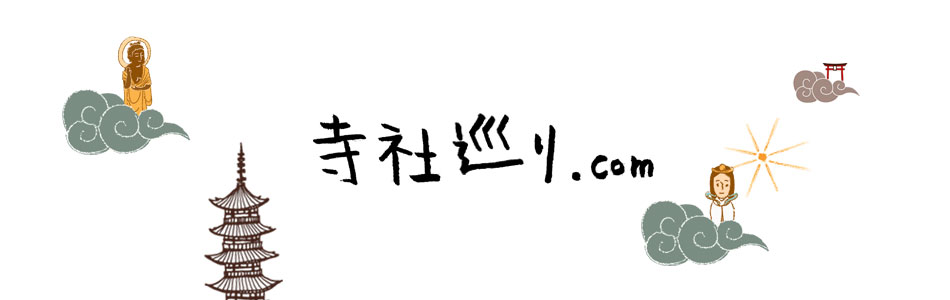京都の節分行事で最も人が集まる行事の一つ、吉田神社の節分祭に行きました。
吉田神社は節分発祥の社といわれていて、たくさんの人が厄除け祈願にやってきます。
周辺は交通規制が行われ、屋台もたくさん出て盛り上がるのですが、その中の一つに、河道屋のれん会の「年越そば」があります。

場所は、料理飲食の神様を祀る境内社「山陰神社」のすぐ横。
昭和27年から毎年2月2~3日に出店しているそうです。
「年越しそば」といえば、普通は大晦日に食べるもの。
ここではなぜ節分の日に「年越そば」なのでしょうか?
それにはちゃんと理由がありました。
「年越そば」はそもそも節分の日に食べるものだった!

実はそもそも「年越そば」というのは、2月の節分の日に食べるそばだったのです。
「節分」は「季節を分ける」という意味で、立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを指します。
なので2月の節分の次の日は「立春」です。
旧暦では立春が新年の始まりなのです。
なので、その前日である「節分」に食べるそばが、年越そばなんですね。
明治に入ってから暦は新暦になりましたので、1月1日が新年の始まりとなります。
なので今では、12月31日に食べるそばが「年越しそば」と呼ばれています。
年越しそばを食べるルーツは江戸時代にあった
年越しにそばを食べる習慣ですが、そのルーツは江戸時代にあります。
江戸時代には、月終わりにそばを食べる風習があったのだそうです。
月終わりのことを「晦日」といいます。
なので、毎月終わりに食べるそばは「晦日そば」と呼ばれていました。
長く伸びるそばは、寿命を延ばし、家運も伸びます。
また、そばは切れやすいので、厄災も切ることができます。
江戸時代の人は、月の締めくくりにそばを食べて縁起をかつぎ、次の月へ運気をつなげていたわけです。
しかしいつしか「晦日」という言葉は廃れ、「晦日そば」も習慣からなくなっていきます。
それでも年を越す大晦日だけは特別なので、今もまだ残っていると考えられているそうです。
晦日は毎月ありましたが、大晦日は年に一回。
大晦日は年を越すので「年越しそば」と呼ばれるようになったのでしょう。
河道屋のれん会の年越しそば

こちらが河道屋のれん会の年越しそば。
650円です。
山葵大根おろしと海苔のシンプルなそばでした^^
わさびは抜いてもらうことができますが、ほんのり香る程度で食べた後に広がります。
個人的にはあった方がおいしいと思います。
ちなみに、なぜ吉田神社で年越しにそばなのか?というと、吉田神社は厄除け発祥の社だからです。
上で述べたように、そばは厄を落とすと考えられていましたよね。
そういう場所で節分の日に年越しそばを食べるとご利益がありそうですね^^